『仮面ライダー青春譜』 第1章 巨匠との遭遇(3)
●松本零士氏の不遇時代
喫茶店を出たぼくたちは、桜台駅で西武池袋線の電車に乗った。行き先は石神井公園。「しゃくじいこうえん」と読むらしい。桜台からは四つ先の駅だった。
石神井公園駅でバスに乗り、東映撮影所前で下車すると、撮影所の脇の細い道をまっすぐに北に向かって歩く。
次に訪問する松本零士先生のお宅は、あちこちに畑が広がる練馬区大泉学園町の一角に建っていた。
やはり新築の大きな家で、案内された応接間には暖炉まであった。
ソファに座って待っていると、上品でにこやかな笑みを浮かべた女性が、紅茶を運んできてくれた。エプロンをつけているが、お手伝いさんではなさそうだ。
紅茶の受け皿には、スプーンと一緒に、輪切りになったレモンが載っていた。このレモンが何をするものなのか、ぼくには見当がつかなかった。わが家でも紅茶を飲むことはあったが、入れるのは砂糖だけだったからだ。
「冷めないうちにどうぞ」
紅茶を出し終えた女性が、そう言い置いて応接間から出ていくと、ぼくの耳元で菅野がささやいた。
「牧先生だよ」
「え? もしかして松本先生の奥さんの牧美也子先生……?」
「そう」
菅野は、当然といった顔でうなずくと、紅茶が入ったカップのなかに、受け皿に添えられていた輪切りのレモンをスプーンに載せて入れた。
ぼくも見よう見まねでスプーンを使ってレモンをすくいあげた。この瞬間は、あの『マキの口笛』の作者でもある牧先生に会えた感激よりも、輪切りになったレモンを落とさないようにカップに入れることに必死になっていた。
紅茶にレモンを入れて飲む習慣があることを知ったのは、恥ずかしながら、このときが初めてだった。田舎育ちのぼくは、喫茶店というものに入ったこともなく、そのためレモンティーの存在も知らなかったのだ。
数分後、
「やあ、待たせてごめん」
といいながら松本先生が入ってきた。
正面のソファに腰をおろした先生は、ぼくの前のティーカップに目をとめた。
「早くレモンを出したほうがいいよ。紅茶の色が薄くなってしまうから」
その言葉に驚いて、両隣に座る菅野や細井たちのカップを見ると、いつのまにかレモンが出され、受け皿の上に置かれたスプーンの上に載っている。レモンを入れっぱなしにしていたのは、ぼくだけだった。ぼくは、あわててスプーンでレモンのサルベージ作業に取りかかった。
レモンを引きあげるのももどかしく、松本先生にもサインをお願いした。しかも、またも図々しく二枚の色紙を差し出したのだ。
「何がいいの?」
ぼくが出した色紙を手にして松本先生が訊いた。ぼくは、すかさず答えた。
「零戦をお願いします!」
「え?」
松本先生が、一瞬、目を丸くしたが、その顔は、すぐに微笑みに変った。どうやらこちらが年季の入った松本ファンであることに気づいてくださったらしい。
「長いあいだマンガ家をしてるけど、零戦を描いてほしいといわれたのは初めてだなあ……」
松本先生は、照れ笑いしながら青の硬質色鉛筆で色紙に当たりをとると、黒のマジックインクで下絵をなぞりはじめた。
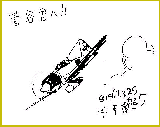 「最近、こういうマンガの注文が少なくなっちゃってねえ……」
「最近、こういうマンガの注文が少なくなっちゃってねえ……」
突然、松本先生の口調が寂しげなものに変わった。「注文が来るのは犬っころのマンガばかりなんだよなあ……」
当時の松本先生は、少年マンガは松本あきらのペンネームで執筆し、奥さまの牧美也子先生と少女マンガを合作するときのみ、松本零士の名前をつかっていた。少年マンガでは、『電光オズマ』『潜水艦スーパー99』『ララミー牧場』といったSFマンガやアクションマンガを描いていたが、ぼくが惹かれたのは、誰よりも精細なメカニズムの描写だった。
松本先生のメカは、潜水艦から拳銃に至るまで、どれもこれもがリアルで、しかもカッコよくデフォルメされていた。小学生のときに、そんな松本マンガのメカ描写にしびれたのが、自分でマンガを描きはじめるきっかけでもあったのだ。
とりわけ航空戦記マンガに描かれた零戦やグラマンの絵の精緻さは、他のマンガ家の追随を許さなかった。旧日本陸海軍の航空機については、元陸軍航空隊整備兵出身の、わちさんぺい氏の絵も素晴らしかったが、松本先生の絵は、それにスマートさが加わっていた。わちマンガのメカが、リアルではあっても、どこかのんびりとしているのに対し、松本マンガに登場するメカは、どこまでもスマートでクールだった。そこに新しさがあったのだ。
小学生のとき、松本先生の戦記マンガに遭遇したのがきっかけでマンガを描くようになったぼくにとって、色紙に零戦の絵を描いてもらうのは、悲願のひとつでもでもあった。
しかし、「冒険王」に連載されていた『潜水艦スーパー99』(一九六四~六五年)あたりを最後に、少年マンガからは遠ざかっていた。「犬っころのマンガ」と自嘲気味にいわれたのは、『その名はテス』などの松本零士名義で描かれた少女向けの動物マンガが仕事の中心になっていたからだろう。奥さまの牧美也子先生と合作した動物マンガも多かった。
「またメカの出てくるマンガを描けたらいいんだけどねえ……」
松本先生は、ブツブツとつぶやきながら二枚目の色紙には、犬っころならぬ子猫の絵を描いてくれた。少女雑誌では、子犬や子猫の登場する哀しいマンガが人気を集めていた頃で、松本先生も、その人気に便乗するような作品を描いていた。松本先生にとっては不遇の時代だったのだ。

松本先生が色紙を描き終わるのを待って、ぼくは自作マンガの原稿を取り出した。先ほど石森章太郎先生にも見てもらった原稿だ。石森先生には、時間がないこともあってペンタッチの批評しかしてもらえなかったが、松本先生は、鉛筆を取り出して、具体的なチェックをしてくれた。
最初に見たのは当然ながらトビラだった。そこには「シークレット・エィジエントマン」という恥ずかしいタイトルが描かれている。
「ほお、自分でタイトルまで書いているのか。でも、プロになると雑誌の編集部に詰めている版下屋さんが、タイトル文字をレタリングしてくれるから、自分で描く必要はなくなってしまうんだよ」
その言葉を聞いて、ぼくは隣にいる菅野の顔を盗み見た。去年、〈ミュータント・プロ〉に入会申し込みをしたとき、送ったカットの絵に「レタリングがなっていない」という酷評をしていたのが菅野だったからだ。
――プロになれば、レタリングの技術なんて必要なくなるんじゃないか……。
そんなことを考えながら菅野の顔を横目で見たのだが、松本先生は、まるでぼくの心中を見透かしたかのように、次のような言葉を発したのだった。
「でも、手塚先生も、タイトルは自分で描いてるだろ? 石森さんもそうだね。タイトルを版下屋さんにまかせるようになったのは、つい最近のことで、本来はマンガ家が描くべきものなんだよ。タイトルだって作品の一部なんだからね」
「は、はい……」
ぼくは背中に冷や汗が流れるのを感じながら小声で答えた。
松本先生は、その間も、ぼくのマンガを読み進めていた。
「飛行機は、もっとパースを極端にしたほうがカッコよくなるよ」
こんな構図の取り方まで、具体的に原稿に描き込んでくれるのだ。あまりにも感激したせいか、ぼくの記憶は、このあたりで途絶えてしまっている。どうやって辞去したのかも、まるで憶えていないのだ。
記憶がよみがえるのは、松本先生のお宅から徒歩で向かった久松文雄先生のお宅の玄関先だった。
※画像をポイントすると説明が表示されます。画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
コメント
さっそく楽しみに読ませてもらっています。
松本零士氏の飛行機の描き込み、興味深く読みました。
マンガ技術の技術に関してはまったくの素人ですが、すごくおもしろいです。
以前、この雑記帳でも書かれていた石森氏の技術論(http://www.m-sugaya.jp/blog/archives/000060.html)も、具体的に読めるとうれしいなあと思いました。
つづき、楽しみにしてますね。
投稿者: 山口芳宏 | 2005年05月05日 21:01